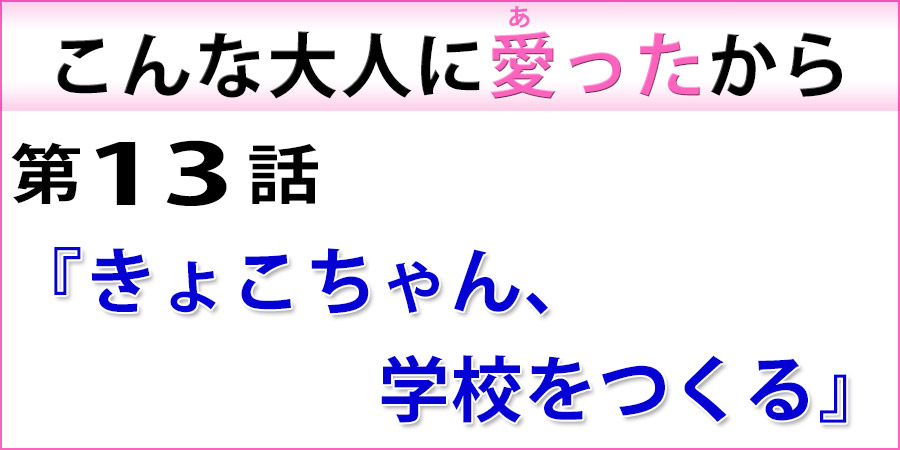
日本史にかがく花園学園のスタート
最近のきょこちゃんグループのお気に入り遊びは、学校ごっこです。学校から帰ってきて宿題をしない子供たちがいるので、学校ごっこの中でさせてしまおうというアイデアで始めたのですが、今では学校に行っていない小さな子供たちまでも、足し算、引き算、九九まで出来るようになってしまいました! 先生は3年生が3人、自分の習ったことを教えます。小さな子供まで『2・1が2、2・2が4、・・・・・・』と暗唱させられ先生役の3年生は必然的に勉強ができるようになってきました。
フサ子ちゃんも、自分が先生になって宿題をみんなにさせて済ませますから、本物の学校で先生に叱られなくなってきました。きょこちゃんは自分の宿題はお昼休みにしてしまいます。
「だって帰るとやらなきゃならないことが、どっさりあるんですもん」
テストを作ったり、給食を用意したりと、学校ごっこには準備が必要です。給食には頭を悩ませてしまいました。人数が増えたので、以前のように自分の給食を持って帰るのでは足りません。そこできょこちゃんは御櫃に入っているご飯に目をつけました。
米所で育ったお父さんはどんなに貧乏をしても、美味しいご飯さえあれば生きていけるという人でしたから、お米だけはいつもたっぷり炊いてあったのです。
炊いてあるご飯を人数分おにぎりにして、お味噌をぬります。ラーメン屋食堂でラーメンにのせる板海苔が缶に入っていたので、それを花の形に切り抜き、お味噌をぬったおにぎりに貼り付けて出来上がりです。そんなわけで板海苔は切られてしかも、クズクズになっているのでお母さんは不思議に思っていましたが・・・・・・。
きょこちゃんたちの学校名は、日本史にかがく花園学園という誇らしい名前でした。ですから、たとえ給食のおにぎりといえども、格調高く花形のお海苔が必要だったのです。
なんで“日本史にかがく”なんだと思います? それは、ある広場に時々、出版社の製本工場が印刷ミスや脱字のある本を破棄していくのですが、その中に〔日本史にかが く偉人物語〕というシリーズ本が入っていました。フサ子ちゃんはその「シリーズ12巻」を、本の好きなきょこちゃんのためにゲットしてきてくれました。
「あんさぁ、大変だったんだから。この本は新品ですごくきれいじゃん。みんな目の色変えて狙ってたんさ」
実は縁日の屋台で本を売る人々は、こうした売りに出せない本をどこからか仕入れてきて、安値で売っていたのです。フサ子ちゃんのお父さんはテキ屋さんなので、その筋の情報に詳しいのです。
「まあさ、父ちゃんもたまには役に立つってことさ」
と嬉しそうに持ってきてくれたのです。
〔日本史にかが く偉人物語〕の脱字は何だろう? きょこちゃんは考えました。読んでみると本のはじめの言葉に“国を動かし、科学や芸術の分野で活躍した偉人たちの物語です”と書かれていました。ですからきょこちゃんは、この本が正しくは〔日本史にかがく(科学)偉人物語〕なのだ、と思いました。しかし、印刷ミスで「かが く」になってしまったから、販売されずに捨てられることになったんだろうと想像しました。
本当は「かがやく」だったのですが、そんなこととは思いもしませんでした・・・。
という訳で、みんなの学校ごっこの学校名を決める時、国を動かして科学や芸術の世界で偉人となる人が育ち、日本史に残りますようにという思いを込めて、「日本史にかがく花園学園」としたのです。
きょこちゃんが名前を決める時のいきさつを全部話すとフサ子ちゃんは手を叩いて喜びました。
「あったまいい・・・! あんたホントに頭いいんだねぇ・・・」
ネーミングの理由が自分のゲットしてきた本にあることを、とても誇らしく感じていたのです。
こうして名前が決まり、土曜日には給食もある“日本史にかがく花園学園”はスタートしました。
月・水・金曜日は5時間目まであるので、火・木・土だけの学園です。生徒たちは全員制服としてネクタイをすることにしました。いつか見たガールスカウトの制服がとってもかっこよかったので、その中のネクタイだけでも真似をしたかったのです。
ネクタイを作る布もフサ子ちゃんが調達してくれました。
「アタイさぁ、こんなに役に立つなんて、自分でもビックリさ」
と持ってきてくれたのは、テキ屋さんが屋台の上に敷いて商品を並べる赤い布でした。
「ホントはさぁ、青い布がきれいだったんだけどさ、父ちゃんがそれは今使ってるからなんねぇって言ってさ、この赤いのは前に使ってたけど色焼けしたから捨てるところだったんさ」
フサ子ちゃんの言葉遣いは相変わらずでしたが、赤い布は大いに歓迎され、三角巾に切ってみんなのネクタイが作れました。
ただ1つだけ困ることは、汗をかくと赤い染色が落ちて首の周りにつくことなのですが、そんなこと誰も気にしませんでしたので、みんなは赤いネクタイを喜んで首に巻いていました。みんな仲間という連帯感になったのです。
(続く)


